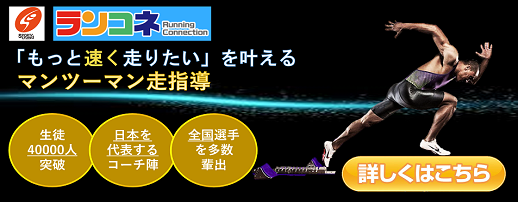高平慎士直伝!スタートダッシュの考え方
高平慎士直伝!スタートダッシュの考え方
福井県陸上競技場リニューアルメモリアルセレモニーにおいて開催された高平慎士選手による陸上競技クリニック。
今回は高平選手がスタートダッシュ、走り方、走りについての考え方についてお話している映像です。
前半は高平選手が考える走り方。後半はスタートの構え方についてです。
それでは前半について。
人間にはスタートが得意、中間疾走の加速力が売り、後半まで走りきれるなど自分の長所があると思います。逆に短所も持っていると思います。
よく中学生、高校生はスタートが苦手です。スタートが速くなりたいです。など、ある特定の部分に考えが固まりがちです。スタートは100mのうち、5パーセント程度の重要度といいます。残りの95パーセントを伸ばせる方法を考えたほうがトータルで速くなれるのではないかという考え方です。
もちろんスタートは短距離走において重要な部分で、速い方が良いに決まっていますがスタートが速いから100mすべて速いということとは言い切れません。
スタートについて追及することも大切ですが、トータルで速い方法を見つけて練習をしていくことが大切になります。
次にスタートの構えです。
高平選手は過去にアメリカのトム・テレツ氏から指導を受けていました。トム・テレツ氏はアメリカの短距離・走幅跳選手であるカール・ルイスを指導した名手です。
トム・テレツ氏の論文では前足の膝の角度が90度になるような位置で前足の位置を決める。前足の膝の先端がスタートラインに乗るような位置で構え、胸が地面と平行になるように構えることが重要といいます。
さらにセットの瞬間に後ろ足のかかとをブロックから浮かせるようにしています。ピストルがなった瞬間に後ろ足のかかとでブロックを踏むことでスタートで勢いを意識的につける癖をつけているとのことです。また、前足の角度は一歩目が出た時に足先から頭まで一直線になる角度で出れるようにすると人間の体の構造が上手く使える角度だとおっしゃっています。
何度も映像を見て高平選手がおっしゃっていることを理解した後に自分の身体で実践してみましょう!なにかコツがつかめる人がいるかもしれません!
藤光謙司選手(ゼンリン・200m歴代2位:20秒13)や北京五輪4×100mリレー銅メダリストの高平選手のようなスタートが身に着くように練習していきましょう!
この映像は「福井陸協」様の作品です
【新着】関連記事
この記事を見た人はこんな記事も見てます。
-

最新トレーニング!アサファ・パウエル、2016年のはじまり
先日の室内大会において圧倒的な勝利を収めたアサファ・パウ...
2016年03月01日
-

400m女王vs1500m女王
全国高校総体、和歌山インターハイ女子800m決勝は女王同...
2015年08月02日
-

アリソンのトレーニング②
アリソン・フェリックス選手のトレーニング第2弾! ...
2015年10月26日
-

どこまで伸ばせる!?距離が長いボックスジャンプに挑戦
以前、ハードルジャンプ編を書きましたが、今回は「ボ...
2016年01月04日
-

最大スピードを向上させる!【ハードルを使った加速ドリル】
今回は加速区間の練習を紹介します。 加速区間とはスター...
2018年03月06日
-

股関節の速い切り替え動作を身につける!【ギャロップ走】
今回は股関節を速く切り替える動作を身につけるためのスプリ...
2019年02月19日
-

腹筋を鍛え、体の柔軟性を高めよう!ワームウォーク
今回は腹筋を鍛えながら、体(ハムストリングス)の柔軟性を...
2016年05月05日
-

【スタートダッシュで差をつける】0からのスタートを速くするドリル
-

世界の走りを見て学ぶ!トップスプリンターの100m
-

冬季トレーニングについて
-

素早いランジをしてみよう!ランジトレーニング
-

砂浜ダッシュの効果
-

【まっすぐ振るのは逆効果かも…】腕をまっすぐ振って「速くなる人」と「速くならない人」の違いとは?
-

ハンマー投 日本王者のパワーマックス
-

グライド投法
-

瞬発力を鍛えよう!スクワット~ボックスジャンプ
-

ハードル 股関節補強
-

日本歴代6位から技術を盗め!走高跳ドリル
-

ステファンホルム・Hジャンプ
-

【スタートダッシュで差をつける】0からのスタートが速くなるドリル
-

【下半身&バネの強化】上半身と下半身を連動させる!「ハードルジャンプ」
-

コーナーマーク走
-

トップアスリートの高跳びドリル
Category New/カテゴリー新着情報
 【たった3分で追い込める!】最強腹筋トレーニングメニュー「全方向から鍛えられる計6種類の腹筋サーキット...詳細
【たった3分で追い込める!】最強腹筋トレーニングメニュー「全方向から鍛えられる計6種類の腹筋サーキット...詳細 【1日3分】室内でできる全身トレーニング(中級編)アスリートが考えた3分『全身トレーニング』 ...詳細
【1日3分】室内でできる全身トレーニング(中級編)アスリートが考えた3分『全身トレーニング』 ...詳細 【練習メニュー】下り坂でスピードトレーニング(4種)自主練や部活で使えるシリーズ第三弾『下り坂』の...詳細
【練習メニュー】下り坂でスピードトレーニング(4種)自主練や部活で使えるシリーズ第三弾『下り坂』の...詳細 【練習メニュー】上り坂でスピードトレーニング(6種)自主練や部活で使えるシリーズ第二弾『上り坂』の...詳細陸上競技
【練習メニュー】上り坂でスピードトレーニング(6種)自主練や部活で使えるシリーズ第二弾『上り坂』の...詳細陸上競技 【練習メニュー】下り坂でスピードトレーニング(4種)自主練や部活で使えるシリーズ第三弾『下り坂』の...詳細
【練習メニュー】下り坂でスピードトレーニング(4種)自主練や部活で使えるシリーズ第三弾『下り坂』の...詳細 【練習メニュー】上り坂でスピードトレーニング(6種)自主練や部活で使えるシリーズ第二弾『上り坂』の...詳細
【練習メニュー】上り坂でスピードトレーニング(6種)自主練や部活で使えるシリーズ第二弾『上り坂』の...詳細 【恐怖を超えた究極のスタート】コールマンから学ぶスタートの極意クリスチャン・コールマン(Christian ...詳細
【恐怖を超えた究極のスタート】コールマンから学ぶスタートの極意クリスチャン・コールマン(Christian ...詳細 【長距離ランナー必見!】ランナーにオススメのトレーニング集オレゴンプロジェクト所属のゲーレン・ラップ選手...詳細ケガ・ストレッチ
【長距離ランナー必見!】ランナーにオススメのトレーニング集オレゴンプロジェクト所属のゲーレン・ラップ選手...詳細ケガ・ストレッチ 下向肘上げ 改善エクササイズ【フィジカルチェック用】「フィジカルチェック項目:下向肘上げ」の点数が...詳細
下向肘上げ 改善エクササイズ【フィジカルチェック用】「フィジカルチェック項目:下向肘上げ」の点数が...詳細 下向胸上げ 改善エクササイズ②【ケガ予防フィジカルチェック用】「フィジカルチェック項目:下向胸上げ」の点数が...詳細
下向胸上げ 改善エクササイズ②【ケガ予防フィジカルチェック用】「フィジカルチェック項目:下向胸上げ」の点数が...詳細 下向胸上げ 改善エクササイズ①【フィジカルチェック用】「フィジカルチェック項目:下向胸上げ」の点数が...詳細
下向胸上げ 改善エクササイズ①【フィジカルチェック用】「フィジカルチェック項目:下向胸上げ」の点数が...詳細 【梅雨の季節の体調管理】アスリートに必要な知識蒸し暑く過ごしづらい季節がやってきました。そう...詳細サッカー
【梅雨の季節の体調管理】アスリートに必要な知識蒸し暑く過ごしづらい季節がやってきました。そう...詳細サッカー![エムバぺ(フランス代表)はなぜあんなに速いのか!?[陸上コーチによる解説]](https://scontent-nrt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/36517387_1835818623123141_660013401107333120_n.jpg?_nc_cat=0&oh=235d604d3aa510071bdcd0cc4cf42dc7&oe=5BEAD195) エムバぺ(フランス代表)はなぜあんなに速いのか!?[陸上コーチによる解説]先日4年に1度のワールドカップが行われ、日本代...詳細
エムバぺ(フランス代表)はなぜあんなに速いのか!?[陸上コーチによる解説]先日4年に1度のワールドカップが行われ、日本代...詳細 【W杯でも活躍!】サッカーイングランド代表が行なった〇〇を使ったトレーニング2018年ワールドカップ盛り上がりましたね! ...詳細
【W杯でも活躍!】サッカーイングランド代表が行なった〇〇を使ったトレーニング2018年ワールドカップ盛り上がりましたね! ...詳細 【W杯でも大活躍】レアル・マドリードのトレーニング欧州チャンピオンズリーグ3連覇、今回のW杯でも...詳細
【W杯でも大活躍】レアル・マドリードのトレーニング欧州チャンピオンズリーグ3連覇、今回のW杯でも...詳細 【世界トップの瞬発力!】メッシ選手のアジリティトレーニング【間も無くW杯開幕!】5度のバロンドール受賞、5回のチャンピオンズリ...詳細栄養・食事
【世界トップの瞬発力!】メッシ選手のアジリティトレーニング【間も無くW杯開幕!】5度のバロンドール受賞、5回のチャンピオンズリ...詳細栄養・食事 【瞬発的エネルギー!】クレアチン摂取タイミングのポイントと注意点クレアチンはアミノ酸の一種で、筋肉内のエネルギ...詳細
【瞬発的エネルギー!】クレアチン摂取タイミングのポイントと注意点クレアチンはアミノ酸の一種で、筋肉内のエネルギ...詳細 【骨強化に】身長を伸ばす為に必要な栄養素【Jr世代は特に大切!】色々な競技の上で、身長が高いということが有利に...詳細
【骨強化に】身長を伸ばす為に必要な栄養素【Jr世代は特に大切!】色々な競技の上で、身長が高いということが有利に...詳細:max_bytes(150000):strip_icc()/GettyImages-96586038-58a4bb963df78c4758eaa03e.jpg) 【金メダリストの朝ご飯にも!?】正月によく食べるお餅の栄養&効能お正月はおせち料理やお雑煮など、お餅を食す機会...詳細
【金メダリストの朝ご飯にも!?】正月によく食べるお餅の栄養&効能お正月はおせち料理やお雑煮など、お餅を食す機会...詳細 【身体の調子を整える】サプリメントアプローチ「ZMA」普段の食事から摂取するのが難しい栄養素がある場...詳細野球
【身体の調子を整える】サプリメントアプローチ「ZMA」普段の食事から摂取するのが難しい栄養素がある場...詳細野球